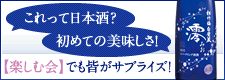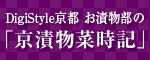【その9】茶の道具/茶杓(ちゃしゃく)と柄杓(ひしゃく)
 まだまだ不馴れな私がお茶をたてるときに、一番緊張するのは、炉から柄杓で水を汲むときと、お棗(なつめ)から茶杓で抹茶をすくう時なんですね。私の先生や諸先輩方の振舞いはそれはそれは優雅なんですが、私の場合、どうもいよ~っと挑むような気合いが入ってしまうんです(笑)。
まだまだ不馴れな私がお茶をたてるときに、一番緊張するのは、炉から柄杓で水を汲むときと、お棗(なつめ)から茶杓で抹茶をすくう時なんですね。私の先生や諸先輩方の振舞いはそれはそれは優雅なんですが、私の場合、どうもいよ~っと挑むような気合いが入ってしまうんです(笑)。
ところが、柄杓はもともと弓師が作ったといわれているというのを知って納得しました。私の気合いが入るのは、なにも緊張からではなく、弓矢の手が取り入れられたあの作法にあるんですよね!?・・・「柄杓を扱うときの要点は、お腹に力を入れて、手先は軽く、力を抜ききって扱うこと」と、千宗室氏も教えられています。これがまた難しいんですが、まさに武道の精神と同じなんです。置く時、引く時、水を切る時とその場面で柄杓は名前をそれぞれ持ちます。置柄杓は弓に矢をつがえるときの心、引柄杓は、弓を満月に張ったところの心、切柄杓は矢を放ったところの心、なんだそうです。
また、もっとも茶人の茶徳が表れているといわれるのが、茶杓なんです。その一本にすべてが表現され、茶人が自由に創作力を発揮できるお道具というわけです。初期には、象牙やべっ甲などの素材でつくられたものもあったようですが、村田珠光(じゅこう)によって竹に移され、やがて長さが様々であったものが千利休によって18cm前後と定められたそうです。さらに、竹の節にも好みがあって、珠光は節なし、紹鴎は元節、利休は中節といわれます。そして小掘遠州になると、さらに「銘」がつけられ、二重、三重にも箱がつけられるようになりました。
茶の湯の教えや道具扱いの心得を教示したといわれる「利休居士道歌」では、どんな道具でも、手順で他の道具にうつる時は、その前の道具を恋しい人と別れるように、名残惜しく扱わなければならないと教えています。なかなか、粋なたとえです。簡単に次から次へといくのも素っ気無いし、また未練たらたらでもいけないということなんですよね。これはますます難しいですね。(笑)
一連の作法のなかで、茶碗に水や湯、抹茶を入れる時、どんな道具であれ、なにか自分自身の全責任をもって、新しい世界を切り開くようなそんなかんじがするんです。だからこそ、少しでも自分の好みのお道具で、お茶をたてる。また、その道具がじつに心地よく音をたてる。私達の五感を刺激しつつ、より一層その場を演出してくれるというわけなんです。道具は、人の振る舞いと一体となって、亭主を中心に空間をつくります。茶室というのは、お茶をたてるために、最小限の空間、亭主と客、お道具がおさまるだけの空間を囲んだもの、それだけなんですね。まぁ、ちょっとでもいい道具といい茶室でならば、うまくお茶をたてられそうな気がするんですけどね。本当のところは・・・。