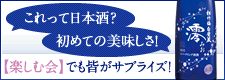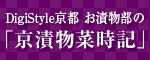【その7】茶室の空間/茶花
「花は野の花のように」という教えが利休の残した七則にあります。野の花が、自然に野に咲いているそのままの姿を映す心を生けるものとされています。茶花は決してフラワーアレンジメントのように、美を構成するものではありません。また、野原に咲いているそのままの眺めを再現することでもないのです。たった一輪であっても、その花の姿のなかに、すべての生命(いのち)や風景が宿されているものなのです。
茶花を入れる場合にまず求められるのは、花を入れる人自身が素直な心に徹することなのです。美しくみせようとする技術的なものではなく、花そのものの自然な姿を生かしていれることや、余情をいれることが大切とされています。余情というのは、とても日本的な美学が根底にありますよね。情報公開といわれている今の時代、なんでもオープンにするのが善しとされてしまうと、心に秘めるという日本人特有の美徳が忘れられていくような気がします。とくに私達女性は開放的になって、いいたい放題の世の中になってきています。でも、言わないで残してあるからこそ、風趣があるということを、茶の湯を通じてあらためて感じ入るようになりました。
その点、私達の住む京都は、どことなく懐が深くて秘する町と言えるような気がします。それは、町家の連載でもお話してきましたが、間口が狭く奥に路地が長い町並みにも関係することなんですね。茶室も同様で細長く続く露地から入り、飛び石をつたい、躙口(にじりぐち)から席入りする。どこか京の町を縮小したかんじですよね。
 茶室にあるものはどんなに高価であれ、すべて静物ばかりですが、唯一茶花だけが自然の生命のあるものなのです。その昔、千利休が豊臣秀吉に美しい見事な朝顔が咲いたので、ぜひ御覧くださいと招いたそうです。ところが、庭にはどこを探しても、一輪も朝顔が咲いていない。どういうことだろうと訝しがった秀吉が、茶室に入ると、そこには一輪の大輪の朝顔が生けてあったそうです。利休は、そのたった一輪の朝顔を見せるために、庭に咲いていたすべての朝顔を摘み取ったのです。事情を悟った秀吉は、これほどの贅沢はこのうえないとたいそう喜んだそうです。
茶室にあるものはどんなに高価であれ、すべて静物ばかりですが、唯一茶花だけが自然の生命のあるものなのです。その昔、千利休が豊臣秀吉に美しい見事な朝顔が咲いたので、ぜひ御覧くださいと招いたそうです。ところが、庭にはどこを探しても、一輪も朝顔が咲いていない。どういうことだろうと訝しがった秀吉が、茶室に入ると、そこには一輪の大輪の朝顔が生けてあったそうです。利休は、そのたった一輪の朝顔を見せるために、庭に咲いていたすべての朝顔を摘み取ったのです。事情を悟った秀吉は、これほどの贅沢はこのうえないとたいそう喜んだそうです。
この逸話は利休のその徹底した美学を語るひとつの代名詞にもなっていますが、たった一輪のために、多くの朝顔が犠牲になるわけですから、傍若無人と思われるかもしれませんね。しかし、彼は庭の朝顔を摘み取るときにも、ひとつひとつ丁寧にその生命の重さを感じながら、美しく咲いてくれた朝顔に感謝の心をこめて別れを惜しんでいたに違いありません。利休は、表層は静かではありますが、心のなかはすべての生命を尊ぶ強い精神があふれていたように思います。
花について語っている言葉に、こういうものもあります。
『秘すれば花なり秘せずは花なるべからず』
これは世阿弥の書き残した『風姿花伝』の中の、よく知られた一節です。
『ただ珍しさが花ぞと皆人知るならば、さては珍しきことあるべしと思ひ設けたらん見物衆の前にては、たとひ珍しきことをするとも、見手の心に珍しき感はあるべからず。見る人のため花ぞとも知らでこそ、為手の花にはなるべけれ。されば見る人は、ただ思ひのほかに面白き上手とばかり見て、これは花ぞとも知らぬが、為手の花なり。さるほどに人の心に思ひも寄らぬ感を催す手だて、これ花なり。』
これらは、能を伝授するために記したもので、「意外性が感動である」と観客が知ってしまえば、その効果は激減すると言っています。意外性など期待していないときに、そして演技者の側も、意外なことなど起こすつもりはまったくないというような態度のなかで、ふと予想外のことを起こすと、観客は感動します。
これは、茶の湯の世界でも同じことがいえるのです。茶室が舞台であり、亭主と客が演者なのですから。