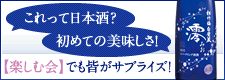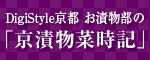源氏物語発見
頃は九世紀。在原行平(ありはらのゆきひら)や業平(なりひら)とほぼ同時代に、源融(みなもとのとおる)がいた。彼は嵯峨(さが)天皇の皇子。臣籍降下して源氏を賜った。
左大臣となって「上なき位にのぼり」、源氏全盛時代の象徴的存在として政治の中心にいた。彼の本宅は六条にあった。有名な六条河原院である。
六町を占有し、院内の池は池ではなく海だった。船をしたてて大阪湾に出、その海水を運び、池に注ぎ込んだのだ。彼は須磨の行平のように、都で塩を作って遊んだ。
信じがたいが本当の話である。

それからおよそ百数十年後。紫式部はこの河原院の上に、光源氏の本宅・六条院を造った。四町であるから実際の河原院より狭いが、それぞれの町を春夏秋冬に割り当て、季節ごとに興趣のある邸宅とした。
これは龍宮にあるという四季の庭の拡大版であり、源融を知っている当時の読者は、融の家とのダブルイメージでもって、池は海にほかならないと想像するだろう。光源氏の六条院はまったくもって「都の龍宮」なのである。
もっとも龍宮の四季の庭の発想は、鎌倉時代成立の『源平盛衰記(げんぺいせいすいき)』にある布引滝伝説中の話で、紫式部の時代にこの発想があったかどうかおぼつかない。
が、明石に滞在していた時、入道の海辺の館が四季おりおりの趣が楽しめるように設計されており、その忘れがたい印象が光源氏の六条院造営に影響したことは疑いない。彼は、都に明石を作ったと言い換えた方がよいかもしれない。
明石のイメージは遠く若紫巻で、すでに龍宮イメージとして定着しているので同じことなのだけれども。
なぜ龍宮なのか。それは六条院が、明石で生まれた明石姫君を養育する場であったからである。では、どうして養育の場は龍宮でなければならないのか。これは明石姫君が天皇を生む人、つまり国母(こくも)であるためである。このことを理解するために、まず国史第一『日本書紀』を見てみよう。
面白いところを切り捨てて、簡単に要点のみを言うと次のような展開となる。天照大神(あまてらすおおみかみ)の子・山彦(やまひこ)が龍宮に赴く。龍宮の姫君・豊珠姫(とよたまひめ)と結婚し皇子をもうける。その皇子を豊珠姫の妹・珠依姫(たまよりひめ)が育てる。その後成長した皇子と珠依姫は結婚する。
そして皇子が産まれる。この皇子こそ、初代天皇・神武なのである。すなわち、龍宮は、天皇の母なる故郷。紫式部が徹底して明石にこだわったのは、源氏物語が天皇の本源を語るという海のような深い底意をもっているからである。
桐壺巻で、高麗からやってきた相人(人相見)が、幼い光源氏を見て、
国の親となりて、帝王の上なき位にのぼるべき相おはします人の、そなたにて見れば、乱れ憂ふることやあらん。おほやけのかためとなりて、天下を輔くるかたにて見れば、またその相違ふべし
と、不思議な見立てをしたが、このあたりから振り返ってみると、納得がいく。光源氏は天皇であるが天皇ではない。融のように、臣下にあって国政を牛耳る人でもない。光源氏は、「国の親」なのである。 豊珠姫ともいうべき明石御方と結婚し、生まれた姫君を紫上が、珠依姫のように育てる物語なのである。が、『日本書紀』をそのままなぞっているわけではない。細部は微妙にずらされている。その「ずれ」の中に紫式部の創造がある。 「ずれ」は、生まれたのが皇子ではなく姫君。その姫君が入内するという形に変更している点にある。これは、現実の皇統を正規の軌道に修正しようという目論見に発しているのだと思われる。また、巨大な若菜巻を境に、豊珠姫(=明石)と珠依姫(=紫上)のチェンジを図って、紫上をこの世から切り離し、彼女の神仙化をも企図しているようなのだが、紙数が尽きた。 指摘だけにしておこう。
京都駅から歩いて15分ほど。京都タワーの下を通って東本願寺、その正門前を右折、東に数分歩くと渉成園に到着する。ここは融の六条河原院のあったあたり。すぐ東北に「本塩竃町」という地名が残っているのもうれしい。融が庭の結構を松島塩竃(しおがま)の景に似せて作ったのは有名な話だ。 江戸時代の名工・石川丈山は、融の河原院を十分に意識してこの庭園を設計している。ろう風亭(「ろう」は門構えに良)前の芝に腰をおろして印月池をわたる風に身をまかせれば、誰でも気分は光源氏である。