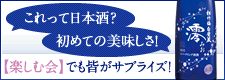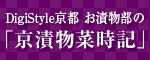源氏物語発見
光源氏死後、光源氏を知る人は少なくなる。その中で、光源氏時代の生き残りである紅梅大納言(光源氏のライバル・頭の中将の息子)は言う。今の世の中、匂だ薫だと言っているが、光源氏に比べたら「端が端」にもかかりはしない。
天下の人気を二分する匂宮(におうのみや)と薫(かおる)は、光源氏とは月とすっぽん、提灯に釣鐘という例えもおこがましいというのである。宇治十帖は、そういうレベルの主人公が繰り広げる物語であるという紅梅巻の枠組みを強く心得たうえで、油断なく読む必要がある。
つまり宇治十帖は「世の常」の人々の修羅場なのであって、ロマンティックな世界とは明らかに違うのだ。

薫は光源氏の子であると思われているが実はそうではない。母の不義によって生まれた男子であった。出生の秘密への疑義が、彼の性格を屈折させる。彼は世を厭い、道心深い。世間の尊敬と信頼を集めている。しかしその道心は、宇治に逼塞(ひっそく)する俗聖(ぞくひじり)・八宮を知り、宇治に通うようになったことで破れてしまう。
宇治には彼をただの人にする美しい姉妹、大君と中君がおり、さらには彼の秘密を保持し、その秘密が入った袋をもって待ち構えていた執念の老婆がいたのである。
秘密を知り、運命を感じた大君との結婚を願った彼は、八宮の死後、死に物狂いになる。大君は薫が嫌いであったわけではない。すでに二十五歳であったし、容色の衰えた自分は薫にふさわしくない。自分より若くて美しい中君と結婚してほしい。自分はふたりの世話をしたい、と考えた。
が、薫は大君しか見ていない。大君の願いを頑として拒み、あろうことか親友の匂宮を宇治に連れて来て、有無を言わせず中君と結婚させる。そして大君に迫るのである。「もうあなたには僕しかいない」。嘆き悲しみ恨む大君を前にして薫は必死になぐさめ弁解せざるを得なかった。
大君は、やむなく中君の世話をするが、はかばかしくない二人の仲を悲観し嘆きを重ねる。嘆きが積もり積もって遂に大君は死ぬ。薫は公務を投げうって看病したが、かいがなかった。いうまでもないことだが、薫と大君は清い仲であった。当時の事情に照らせば異常といえる。光源氏がつぶやいた、生後五十日目の薫への呪文「汝が父に似ることなかれ」が効いているのだと考えると面白かろう。
大君に死なれてみると、後悔の念がふつふつと沸く。なぜ、中君を匂宮に与えたのか。二人とも自分の妻にしてもよかったのだ。その頃、京都に引き取られた中君が匂宮の新しい結婚(光源氏の息子、夕霧の娘・六の君との結婚)に懊悩していた時期であったから、中君のなかで誠実な薫のイメージがふくらむのはいたしかたない。彼女は手紙を書いた。「私を宇治に連れて行ってほしい」。やってきた薫は中君に近づく。しかしこの時、中君は匂宮の子を宿していた。腹帯に触れた彼はあきらめる。一方、薫の下心を知った中君は絶望するが、薫は中君の唯一の後見人であったから、すげなくもできない。もはやこれまで。好色な夫・匂宮ではあるが、世間の人が思っている「幸い人」となる道を目をつぶって選びとるほかはない。中君は強いて「世の常」の人となることを決断したのである。皇子がうまれる。匂宮の真情から考えるに、将来の中君の幸せは確実であろう。
薫は経済的支援をまめまめしく続けながら、大君恋しい思いを中君に訴える。
「私は宇治の八宮邸を寺とし、大君の人形(ひとがた)を作って本尊としたいと思うのです」。
この時、中君がためらいがちに切り出す。
「実は妹がいるのです。あなたの仏さまになるかどうか、自信はありませんが」。
源氏物語最後のヒロインはかくして登場する。浮舟(うきふね)である。その子二十歳。彼女については次回語ることにする。
宇治はJR奈良線、快速を利用すれば京都駅から15分で着く。京阪宇治線は終点。大阪淀屋橋駅から中書島駅乗り換えでおよそ1時間くらいである。宇治八宮邸のあたりには宇治神社があり、その上に世界文化遺産に登録されている宇治上神社がある。小さな寝殿造りになっているので、往時を偲ぶよすがとなろう。近くに源氏物語ミュージアムもある。源氏ファンが集まる場所である。なお、有名な平等院であるが、源氏物語時代にはまだ建っていない。そこは道長の山荘であり、匂宮が桜や紅葉をめでた所のモデルとなっている。