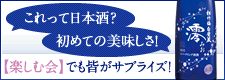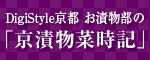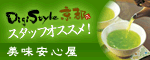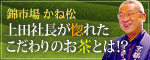店先に湧き出る「醒ヶ井水(さめがいすい)」はなめらかな舌触りで、茶の湯としても重宝される銘水です。創業200余年の『亀屋良長』では、この水を使った繊細な味わいの生菓子づくりを体験することができます。春は桜、夏はあやめ、秋は柿やお月見など、京の四季を彩る自然や風物をかたどる和菓子は、季節をより深く感じることができます。
体験でつくるのは練りきりやあんを使って手軽にできるものです。つくった作品はその場でいただくこともできます。体験の後には、お茶菓子のサービスもあるので、和菓子の世界を心ゆくまで堪能することができます。


洛中三銘水「醒ヶ井水」。室町時代、将軍足利義政にこの水で茶を献じたといわれる。
京菓子は華やかな色合いの「はんなり」とした優美な意匠で、江戸菓子に比べて抽象的だともいわれます。例えば「桜」なら中心部の切れ込みをオシベやメシベと断定せず、「蝶々」の場合は縁に沿って入れたカーブが触角なのか、羽の模様や羽ばたきを表すのかは見る側の感性にゆだねられます。「想像力でお客さまに最後のピースをはめていただく」といった奥ゆかしさが特徴だとも言えます。
同店では「伝統を守りつつ、いかに時代のニーズに合わせて革新していくか」を探りながら、より多くの人が京菓子の世界に触れられるよう体験を受け付けています。

家伝銘菓「烏羽玉(うばたま)」。黒糖の風味がふわりと広がる、上品な和菓子。

駐車場の敷石は京都市電の敷石として、四条通りで昭和47年まで使われていたものだとか。
-
写真歳時 京の四季の花
-
京のお守りおみくじ