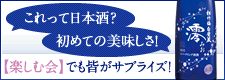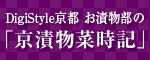義経が平泉の藤原秀衛に迎え容れられたのがいつなのかは定かではないが、治承4年秋、義経が兄頼朝の挙兵に応ずるべく平泉を出立するとき、秀衛はあまり賛成ではなかったといわれている。秀衛には奥州政権確立という想いがあり、そのために義経という持ち札を温存しておきたかったのであろう。義経のたっての希望にやむなく同意したが、信頼する佐藤庄司家の継信・忠信兄弟を随行させたのもそのためであろう。
義経が駿河国黄瀬川で兄・頼朝と対面するのは同年10月だが、この治承4年(1180)から寿永2年(1182)までの2年間には、次に述べるような重要な事件が相次いで起こっており、義経の動静にも大きな影響を及ぼしている。
| 治承4年 4月 | 以仁王の「平家追討の令旨」が諸国の源氏に伝達される。 |
|---|---|
| 同年 5月 | 以仁王・源頼政とともに平家打倒の挙兵をするが敗死する。 |
| 同年 8月 | 源頼朝挙兵するが、石橋山で敗れ安房に逃れる。 |
| 同年 9月 | 木曾義仲挙兵する。 |
| 同年 10月 | 頼朝鎌倉に入り、富士川の戦いで勝利する。 |
| 養和元年閏 2月 | 平清盛没す。 |
| 寿永2年 5月 | 木曾義仲、倶利伽羅峠で大勝し、都を目指す。 |
| 同年 7月 | 平家一門、安徳天皇と神器を奉じ西海に逃れる。同月木曾義仲入京。 |
| 同年 12月 | 義経、頼朝の命により義仲追討の先陣として伊勢国に入る。 |
壽永三年(1184)からの2年間は、義経の絶頂期である。木曾義仲との戦いに始り
一の谷、屋島、檀ノ浦と平家を撃滅し、朝廷から官位を賜るとともに、実質的に鎌倉政権樹立の端緒を開いたのである。
「宇治川の戦」
 義経は寿永三年1月20日、都に居座る木曾義仲を追討するため宇治川に迫った。大手の大将軍・源範頼(義経の異母兄)は、3万5千余の軍勢を率いて瀬田(勢多)から京都を目指し、義経の率いる2万5千余騎は宇治川を北上して直接京都に攻め入ろうとした。平等院から宇治川を渡ろうとする義経軍にたいして、宇治橋を中心とする防禦陣を死守しようとする木曾勢との間で激戦が展開された。
義経は寿永三年1月20日、都に居座る木曾義仲を追討するため宇治川に迫った。大手の大将軍・源範頼(義経の異母兄)は、3万5千余の軍勢を率いて瀬田(勢多)から京都を目指し、義経の率いる2万5千余騎は宇治川を北上して直接京都に攻め入ろうとした。平等院から宇治川を渡ろうとする義経軍にたいして、宇治橋を中心とする防禦陣を死守しようとする木曾勢との間で激戦が展開された。
史上有名な、佐々木四郎高綱と梶原源太義季との先陣争いが繰り広げられたのはこの時である。渡河に成功した義経軍は木曾勢を打破って都に進撃し、義経は数騎を引き連れたのみで、六条西洞院の後白河法皇の許に駆けつけ法皇の守護に成功する。それを見た木曾義仲は瀬田へ落ち延びようとするが、武運つたなく琵琶湖畔の粟津の浜で討死する。
 法皇の御意を得た義経は都で大歓迎され、その名はあまねく知れ渡った。
法皇の御意を得た義経は都で大歓迎され、その名はあまねく知れ渡った。
人知れず鞍馬に隠れ住み、遥か奥州へ難を逃れた若者が都に英雄として帰ってきたのである。義経は歴史に登場した。
「一ノ谷の戦」
 源氏の仲間争いを好機ととらえ、一ノ谷付近に布陣して上洛の機会を窺う平家軍にたいして、源氏軍は時を移さず一ノ谷へ進発した。大手の範頼軍は西国街道から海沿いに、搦手の義経軍は遠く丹波・但馬を迂回して一ノ谷の背後を突く作戦を取った。
源氏の仲間争いを好機ととらえ、一ノ谷付近に布陣して上洛の機会を窺う平家軍にたいして、源氏軍は時を移さず一ノ谷へ進発した。大手の範頼軍は西国街道から海沿いに、搦手の義経軍は遠く丹波・但馬を迂回して一ノ谷の背後を突く作戦を取った。
迎え撃つ平家軍は、生田の森(現・神戸三ノ宮付近)から一ノ谷(現・須磨付近)にいたる東西三里の海岸沿いに布陣、山の手方面にもぶ厚く兵を配置し、海には数百艘の兵船を浮べて万全の防禦陣を構築していた。南は海、北には屏風を立てたような山塊が連なり、一ノ谷から三ノ谷にかけてのこの付近は天険の要害であった。
但馬から播磨を目指して潜行した義経は、三草山の平家前衛部隊を奇襲によって粉砕すると、三木で軍勢を二分して、一隊を一ノ谷の西から攻撃させるため明石方面へと向わせ、自らは三木から福原へと進路を取り、鵯越付近で更に軍を二分し、義経が率いる七十騎は西南に折れて山中深く分け入った。夜を徹してけもの道を進んだ義経は鉄拐山を抜け、2月7日未明、平家の本陣一ノ谷の背後に出た。目の前は山が垂直に削げ落ちたような断崖である。すでに眼下の一ノ谷一帯では敵・味方が入り乱れての激戦の最中であった。眼もくらむような絶壁を馬もろとも駆け下った義経の一隊はそのまま敵陣を急襲した。背後を蹂躙された平家軍は算を乱して敗走し多くの武将が討死した。無官大夫平敦盛が熊谷次郎直実に首を討たれたのもこのときのことである。
この騎馬軍団による大迂回作戦の急襲戦法は、当時の合戦常識を打破る画期的なものであり、義経の武将としての評価を決定的なものとした。
「屋島の戦」
 一ノ谷を放棄した平家軍は、本拠地の屋島へ逃れ、依然として安徳天皇と神器を擁して瀬戸内海の制海権を保持し、京都回復の機会を窺っていた。
一ノ谷を放棄した平家軍は、本拠地の屋島へ逃れ、依然として安徳天皇と神器を擁して瀬戸内海の制海権を保持し、京都回復の機会を窺っていた。
屋島を攻撃し、一挙に平家を殲滅したいと思う源氏軍には水軍の準備は整っていなかった。一ノ谷の勝利からほぼ一年後の文治元年(1185)2月、ようやく船の準備を整えた義経は、朝廷周辺の制止を振り切って屋島攻撃を敢行した。
2月16日、渡辺津(大坂)に船揃えを完了した義経は、折からの暴風雨をついて四国阿波に上陸し、次の日の朝には屋島に到着した。率いる手勢はわずか百五十騎だったという。ただちに屋島の対岸牟礼と古高松の集落を焼払うと、狼狽した平家軍は海上の軍船へ逃れたが、屋島に押し寄せた源氏の軍勢か意外に少数なのを知ると、陸に近づいて激しい弓矢の応酬が展開された。
那須与一の扇の的射ち落としや、義経の弓流しなどのエピソードが語られ、義経股肱の家来・佐藤継信が義経の身代わりとなって戦死するのもこの時の戦いである。
やがて源氏の後続部隊が到着すると、平家軍は屋島を放棄して西へ向った。
「檀ノ浦の戦」
 義経によって四国を追われ、中国・北九州の沿岸陸地を源氏の範頼軍に制圧されている平家軍としては、関門海峡付近で乾坤一擲の海戦を挑む以外に執るべき策はなかった。以前から彦島に拠点を築いていた平家随一の勇将・平知盛を総指揮官とする平家の船団は、彦島を出て門司側の田ノ浦に集結し、義経の船団は3月23日早朝には関門海峡の東口にあたる満珠島・干珠島の海域に到達した。
義経によって四国を追われ、中国・北九州の沿岸陸地を源氏の範頼軍に制圧されている平家軍としては、関門海峡付近で乾坤一擲の海戦を挑む以外に執るべき策はなかった。以前から彦島に拠点を築いていた平家随一の勇将・平知盛を総指揮官とする平家の船団は、彦島を出て門司側の田ノ浦に集結し、義経の船団は3月23日早朝には関門海峡の東口にあたる満珠島・干珠島の海域に到達した。
3月24日早朝、いよいよ源平の命運を決する最後の戦いが始まった。平知盛は「戦いは今日が最後ぞ。名こそ惜しめ。命を惜しむな」と全軍を激励した。はげしい矢合せが始ると次第に平家が源氏軍を圧倒しはじめた。午前八時過ぎから東に流れ始めた潮流にのって源氏軍を満珠・干珠の島辺りまで追いつめ、源氏の軍船は陣形をズタズタにされ防戦一方となった。
このとき、義経はかねてから考えていた戦法を指示した。敵船の船頭や舵取りに矢を集中したのである。当時の水上戦の掟を無視したこの戦法によって、平家の船は漕ぎ手を失い波に漂った。折から潮流は東から西へと流れを変え、勝敗はたちまちその所を変えた。海上を駆け回るのは源氏の船のみとなり、主のない平家の船が数知れず漂流していた。
かくして檀ノ浦に追いつめられた平家の滅亡は決定的となった。
 二位尼(清盛の妻・時子)は、安徳天皇と宝剣を抱いて入水し、知盛も「見るべきことは全て見つ」と、最期の言葉を遺して海に沈んだ。「平家物語」が描写するこのあたりの文章は、いまだに人の心を打つ。
二位尼(清盛の妻・時子)は、安徳天皇と宝剣を抱いて入水し、知盛も「見るべきことは全て見つ」と、最期の言葉を遺して海に沈んだ。「平家物語」が描写するこのあたりの文章は、いまだに人の心を打つ。
京都史跡ガイドボランティア協会提供