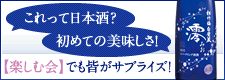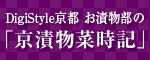安徳帝の身柄と宝剣は失ったものの、平家を完全に打倒し、平宗盛・清宗父子を捕虜として都へ凱旋した義経にたいして、後白河法皇を中心とする朝廷や都の人々は歓迎と賛嘆の声を惜しまなかった。
それ以前、一ノ谷で勝利して一旦京都に帰還した義経に対して、頼朝もその人望と功績を無視することはできず、一旦は京都周辺および近畿での職権代行を認めてはいるが、頼朝の許可を得ずに朝廷から倹非遺使左衛門尉の任官や、従五位下に補任され、さらに院内の昇殿を許されるなどの行為について、次第に嫌悪と猜疑の念を強めていた。
頼朝の推薦ないし許可を得ずに御家人が朝廷によって直接任官や叙任を受けるということになれば、頼朝が目指す政権の基盤は根底から崩れてしまう。まして一族や肉親にだけにその特権を認める事になれば、東国武士団の支持や協力が得られなくなることは明らかである。義経にはそこまでの政治的配慮が欠けていた。自己の功績が認められるのは当然であり、それはまた源氏一族の誉れでもあるという彼の考えは、その後の「腰越状」の文面にもはっきりと述べられている。
ただこの時期には平家追討が完了しておらず、武将としての義経を排除することは出来なかったが、平家打倒が完了したこの時期になると、事態は微妙に変化し始める。
文治元年五月、平宗盛親子を連れて鎌倉に向つた義経にたいして、頼朝は、北条時政に宗盛親子の身柄を受け取らせて、義経には鎌倉に入ることは許さなかった。義経が「腰越状」を提出し、自己の立場を弁明したことは史実にも記載されており、この有名な「腰越状」の全文も(一部にあとで加筆された箇所もあるようだが)現存している。
結局、義経の鎌倉入りは許されず、命じられた宗盛親子の処刑を近江の篠原で行なって京都に帰った義経は、次第に頼朝にたいする不信の念を抱くようになる。
頼朝と義経、この異母兄弟の確執については、様々な見方が論じられているが、流人として伊豆に送られた頼朝も、鞍馬から奥州へと赴いた義経も、孤独のうちに過した年数が長かったことは共通している。源氏の正統という血統以外、自分の手勢も所領もない頼朝にとっては、東国武士団の信頼と協力を持続してゆく以外に平家打倒はもとより、念願である武家政権の樹立などは絵に書いた餅に等しかった。兄弟・血族であっても特別の扱いはしないという政治的立場を崩すことはなかったし、その立場を冷酷に押し通した。一方、自分と親族のことを情愛の世界でしか考えられなかった義経は、そうした広い立場での東国武士団と頼朝の関係を理解することは出来なかった。
同じ流浪の境涯を経てもその環境の相違と個性の違いは、兄弟という絆を裂き、ついには憎悪の世界で相まみえるという悲劇に発展するのである。
土佐坊昌俊による暗殺計画を失敗に終らせた義経は、ついに頼朝との対決姿勢を打ち出し、後白河法皇から「頼朝追討の院宣」を引き出したが、老獪な法皇は、頼朝の武力強圧に屈した形で反対に「義経追討の院宣」を発令するのである。法皇の慰撫を受け入れた義経は、西国武士団を糾合して反頼朝集団を結成しようとして、文治元年11月紀州大物浦から四国を目指して船出するのだが、おりからの暴風雨に船は難破し、僅か数人の供とともに辛うじて紀州に上陸する。
それから4年後には、義経の命運は平泉の地で尽きるのだが、彼の武将としての運命はこの時すでに尽き果てたといっても過言ではない。暴風雨は自然現象だが、2月の屋島攻めにはその暴風雨を利用して勝利を収めたのである。天が義経を見放したと言えば余りにも運命的な見方に過ぎるのだろうか。
鎌倉政権の追捕の網を潜りながら、義経一行の逃避行は、吉野から十津川・奈良・伊勢・鞍馬・京都・比叡山上・北陸から奥州へと、微かな消息を史実に残しながら続くのだが、平泉に再度辿り着くのは文治4年の2月ごろである。
その間、吉野での静御前との別離や、佐藤忠信の奮戦、安宅の関での弁慶の苦心など、様々のエピソードが「義経記」には詳細に記述されており、後年それに基づいて、歌舞伎や能の世界では「義経千本桜」「狐忠信」や「勧進帳」などが世間の人気を集めるが、真偽のほどは定かではない。ただその逃避行は、義経に同情する朝臣や僧侶・山伏たちが陰に陽に庇護し手助けしたことは、史実にも述べられており、鎌倉側でもある程度の情報は得ていたようである。穿った見方ではあるが、頼朝は義経が平泉に向うと見て、巧みにその方向に追い込んだとの説もあるのである。
京都史跡ガイドボランティア協会提供