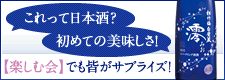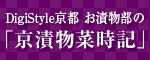源氏物語発見
紫式部が中宮彰子(ちゅうぐうしょうし)の許にいたその隙に、道長が作者の部屋に侵入、原稿を持ち出す。道長はそれを彰子の妹に与えた。という事件が『紫式部日記』に記されている。すでに源氏物語はかなりの部分が世に出ていて、紫式部の令名は一条天皇の知るところともなっていたことが同日記で確認できるから、この未定稿は源氏物語の後半および最終部分であろうと推測される。式部自身は、これで自分の評判が落ちることを心配している。寛弘五年の秋。今から千一年前のことである。
源氏物語の最後の部分が我々にとっても作者にとっても不満であったのは、こういう事情があってのことだと同情できなくもない。が、その後、紫式部が訂正に乗り出したり続編を書いた風もないから、彼女としては細部の不満はあっても、全体の結構はこれでよしとしたものと思われる。

その後、源氏物語はつぎつぎに書き写されてゆき、王朝女性の圧倒的な支持を受ける。女性ばかりではない、その影響力は男性社会にも力強く浸透していった。貴族社会が武家に押されて衰亡してゆくと、貴族が貴族の態をなさなくなってくる。そうなると、「世の常ならざる」最高貴族の全容が描かれ保存されている源氏物語は、貴族が貴族になる唯一の場となって、逆にその価値を不動のものとすることになる。平安末期最高の歌人藤原俊成(ふじわらのしゅんぜい)は言っている。「源氏見ざる歌詠みは遺恨のことなり」。源氏物語は歌人、つまり貴族のアイデンティティであったのだ。俊成の子で、歌神と謳われた藤原定家(ていか)は、源氏物語の定本を作ってその窮乏する生活を支えた。現在われわれが読んでいる源氏物語は定家が校訂した本である。貴族を駆逐した武家勢力も、彼らが貴族たらんとした時、源氏物語がその場としての文化機能を発揮した。この傾向は明治欧化主義の頃まで変わることはない。
源氏物語の研究が本格的に始まったのは鎌倉時代。源氏物語研究の最初の金字塔ともいえる『河海抄』(かかいしょう)には、源氏物語成立伝説が記されている。紹介すると、
大斎院選子(だいさいいんせんし)から中宮彰子に面白い草子を貸してほしいとの申し出があった。彰子は面白いものはないと考え、新作を紫式部に命ずる。式部は観音のご加護を願って石山寺に籠る。時は秋。琵琶湖に映る石山の仲秋の名月。かの地で彼女が見たこの風景が紫式部の脳裡に源氏物語の構想を繰り広げる契機となった。彼女は、思わず仏前の大般若経を拝借、その裏に「今宵は十五夜なり」と書いた。須磨巻の名場面から源氏物語は書きだされていったのだ。光源氏のモデルは安和変(あんなのへん)で左遷された源高明(みなもとのたかあきら)、紫上は紫式部本人。白楽天や菅原道真や在原行平なども考慮されている。この物語は紫式部が一人で全部書いたのではない。藤原道長も一部筆を加えている。最後は藤原行成が清書して源氏物語は成立した。後に、式部は大般若経を書き石山寺に納めた。その経は今もかの寺にある。
この伝説は有名であるけれども、いちいち検討すると不合理で、あくまで伝説の域を出ない。しかし、源氏物語の意味をあらあらと伝えている。源氏物語は平安貴族あげての文化遺産であり、その内容は琵琶湖のように広く静かで深い。学問文治を基本とし、紫式部の志は名月のように高く澄んで世を照らす。仏法に匹敵し凡夫の及ぶところではない。
源氏物語とともに生きた藤原定家は文学の本質を次のように言っている。
詩(うた)はこころを気高く澄ますものにて候。(毎月抄)
JR石山駅から京阪電車に乗り換える。二両連結のかわいい電車に揺られて約三分で石山寺駅に着く。ここから約800メートル、勢田川右岸を南下、徒歩で十分ほどの距離に山門がある。桜とツツジの参道を行き右折、急な石段を登ると硅灰石が林のように立っていて、上に多宝塔が君臨する風景が見える。左に進むと本殿。突き当りに源氏の間があり紫式部の人形が置かれている。伝説とは違い、ここからは琵琶湖も月も見えない。多宝塔まで上がりそのまま進むと勢田川を眼下に月を見る絶好のロケーションに出る。が、琵琶湖眺望は無理である。石山寺から琵琶湖はかなり遠いのだ。四季折々の花々に彩られた山道をゆくと、山腹に紫式部の銅像がある。最近建立された光堂をバックに執筆中の姿、特にその顔が妙にリアルである。本殿で観音様にお参りしたら是非行って見てみてほしい。